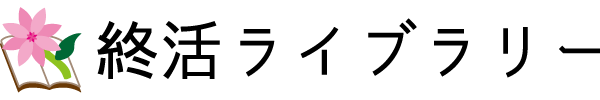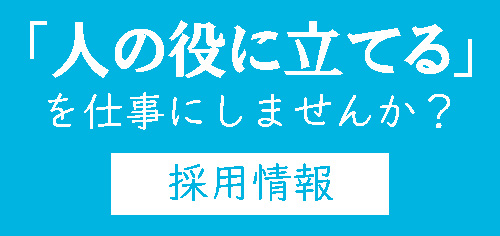赤ちゃんを葬式に連れて行こうと思うと、泣いてしまったりおむつを替えなければいけなかったりと不安要素が大きいです。そのため葬儀や葬式に、赤ちゃんを連れて行ってもいいのかと悩む母親は多いと思います。
そこで今回は、赤ちゃん連れで葬式に参列してもいいのかについてまとめていきます。
葬儀・葬式は赤ちゃん連れでもいい?

赤ちゃんを連れて行っていいかは、遺族との関係によって異なります。親密度や距離感によって、時には配慮しなければいけません。赤ちゃんを連れて行ってもいいのか、遺族との関係ごとにご紹介します。
身内・親戚の場合
身内・親戚が遺族の場合、赤ちゃんを連れて行ってもいい場合が多いです。赤ちゃんを連れていくことは遺族にも負担がかかります。そのため極力預けることがおすすめです。しかし親しい身内や親戚の場合、赤ちゃんにもお別れをさせたい気持ちもあります。その場合は遺族と相談し、参加するようにしましょう。
知人・友人の場合
知人・友人の場合、赤ちゃんを連れていくのは控えたほうがいいとされています。滞りなく葬儀を行いたい遺族に対し、迷惑をかける可能性が高いためです。
しかし、遺族に参加を促された場合や赤ちゃんを預ける相手がいない場合は、赤ちゃんと一緒に参加しても問題ありません。その場合、事前に遺族に相談しておくと安心です。また、参加する時はできるだけ退席しやすい後ろに座っておくようにしましょう。
赤ちゃんを連れていく際のマナー・注意点

赤ちゃん連れで参列する場合には、その時々のマナーがあります。赤ちゃんにとっても普段と全く違う場所。興奮したり落ち着かなかったりすることは、十分に予測できることです。
いつもと違った不測の事態にも対応できるよう、赤ちゃん連れでの葬儀のマナーや注意点を確認しておきましょう。
泣き出したら途中退席
赤ちゃんが泣きだした場合、葬儀や葬式でも途中退席して問題ありません。一般的に葬儀や葬式での途中退席は、極力控えたほうがいいというのがマナーです。しかし赤ちゃん連れの場合、泣いてしまうと式の進行が滞ることも。大切なお別れの場を邪魔しないためにも、途中退席するようにしましょう。
途中退席しやすいように、あらかじめ出入口に近い場所で参列することが重要です。また、泣き出してしまった場合に控室を使えるよう、事前に遺族へ相談しておきましょう。
焼香時は他の人に赤ちゃんを預ける
焼香をする際は気持ちを込めて合掌するためにも、赤ちゃんは誰かに預けましょう。抱っこ紐を使うという手段もありますが、お線香に赤ちゃんが近づきすぎたり、焼香台に触れてしまったりしないよう預けるのが一番です。
預けられる相手がいない場合は、あらかじめベビーカーで参加しておくと安全です。しかしベビーカーは道を塞いでしまうなど邪魔になることも多いため、ベビーカーを持参する場合は周囲へ配慮して使うようにしてください。
長時間に及ぶため火葬場には連れていかない
よほど近しい故人でない限り、赤ちゃんを火葬場には連れていかない方がいいです。火葬場での火葬は2時間以上かかることがあります。長時間に及ぶため、赤ちゃんにも母親にも負担がかかる行事です。赤ちゃんと故人がよほど親しかった場合を除き、自宅待機することが最善といえます。
控室に待機してもいい
どうしても赤ちゃんが落ち着かない場合などは、控室で待機しておいても問題ありません。葬儀や葬式に参列したからといって無理に着席しておく必要はなく、頻繁に出入りするようなら控室で待機しておく方が進行の邪魔になりません。お焼香を行う時だけ他の人に預けて、母親や遺族が無理のない範囲で参加しましょう。
連れていきたい場合は必ず遺族に確認する
赤ちゃんを連れていきたい気持ちが強くても、参加の有無は必ず遺族に確認しましょう。遺族はその故人に対し、どのような葬儀や葬式にしたいかというプランや想いがあります。故人と親しい間柄でも、そのプランにそぐわないようであれば参加を控えたほうがいいです。葬儀は遺族の意向が一番重要であるため、参加してもいいか必ず確認・相談しましょう。
赤ちゃんを連れていく場合の準備と対策

赤ちゃんを連れていくとなったら、まずは入念な準備が必要です。普段持ち歩いているものに加え、必要なアイテムは予備まで用意しておく必要があります。
葬儀や葬式の邪魔にならないためにも、場面ごとに対策を立てておきましょう。ここでは、赤ちゃん連れの準備と対策についてご紹介します。
葬式に持っていく持ち物
赤ちゃんと葬式に参列する場合、以下のような持ち物を持参しましょう。
- マザーズバッグ
- 空腹時のおやつ
- 音のならないおもちゃ
- 予備のスタイ・着替え
- ウェットティッシュ
- 授乳ケープ
- 調乳セット(お湯・哺乳瓶・粉ミルクまたは液体ミルク)
- 防水シート
- おむつとおしりふき
- タオル
- 抱っこ紐
葬儀場には、赤ちゃん用のスペースがないことも予想されます。そのためいつもの外出以上に、入念な準備が必要です。
授乳・おむつ替え・泣き出した際の対策
葬儀場は赤ちゃん用のスペースがない施設も多く、授乳やおむつ替えに苦労することも。そのため、あらかじめ対策しておきスムーズに対応できるようにしておきましょう。
授乳時の対策
授乳する時に、授乳室がなくて困ったということにならないためにも控室などの確保が必要です。そのため事前に葬儀会社や遺族へ確認しスペースを確保しておきましょう。万が一スペースが確保できない場合にも備えて、授乳ケープがあるとより安心です。極力授乳したくないという人は、液体ミルクを常備しておきましょう。ミルクを飲ませる場合でも、必ず一旦退室する必要があります。
おむつ替え時の対策
おむつが濡れたままにならないよう、どこでもおむつ交換できる準備をしておきましょう。葬儀場には、おむつ交換専用のスペースがないことも。その場合は控室などを借りて行います。その際汚れてしまわないためにも、防水シートやタオル、おむつ交換アイテム一式を必ず準備し、おむつ替えを行いましょう。
泣き出した際の対策
突然機嫌が悪くなったり泣き出したりした場合に備え、おもちゃやお菓子を準備しておきましょう。普段からお気に入りのおもちゃやお菓子を準備しておけば、すぐに泣き出すことを防げます。また、ぐずりだしたらすぐに退室することもおすすめです。疲れて眠ってしまった、抱っこ紐で抱っこして参列することもできます。
参列時の赤ちゃんと母親の服装

参列時は赤ちゃんだけでなく、母親の喪服も普段と違った注意点があります。参列した時に焦らないためにも、あらかじめ確認して準備しておきましょう。
赤ちゃんの服装
赤ちゃんの服装は、地味な色の着脱しやすい服装がおすすめです。赤ちゃんの場合、必ず黒を着用しなければいけないわけではありません。原色や目立つ色、白色や柄物は避け、地味な色の洋服であれば問題ないでしょう。
また、葬儀場は室温がどう調節されているか分かりません。そのため着脱しやすく、温かめの服装がおすすめです。室温に応じて洋服を調節できるよう、前開きの洋服だとなおいいでしょう。お菓子や吐き戻しで汚れることもあるため、予備は数枚あると安心です。
母親の服装
母親は授乳や着替えることも考え、前開きのワンピースかセパレートタイプの喪服がおすすめです。まだ授乳が必要な赤ちゃんの場合、ワンピースタイプだと授乳しにくく困ってしまいます。また、赤ちゃんの吐き戻しなどで汚れてしまうことも。そのため着替えやすい喪服を準備しておきましょう。
葬儀に参列しないときの対応
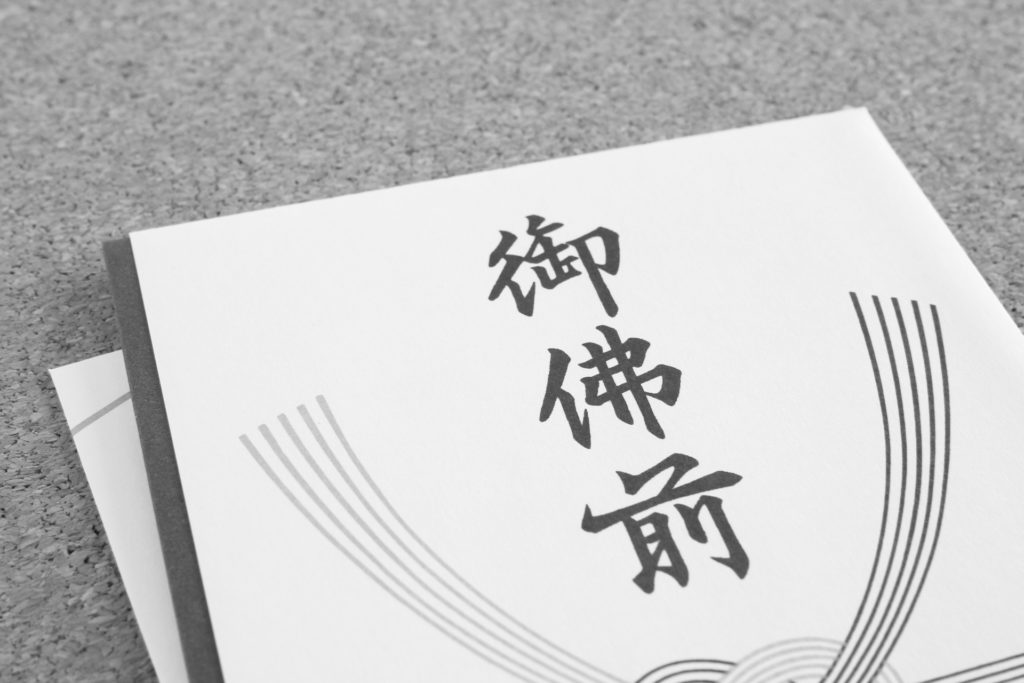
赤ちゃんがいる場合、参列しないという判断も重要な選択肢の一つです。しかし赤ちゃんを預けたり自宅待機していたりする場合、遺族にどう対応すべきが不安に思うことも。夫婦だけ、夫だけ参列する場合はどう対応すべきなのか、ご紹介します。
夫婦・夫だけの参列になると伝える
夫婦だけや夫だけ参列する場合は、遺族に事前に説明しておく必要があります。何の説明もなしに夫婦・夫だけの参列になると、遺族も不安です。そのためどういう理由でどちらかだけの参列になったのか、あらかじめ電話などで説明して参列するようにしてください。
香典は連名で書く
参加するのが夫・妻だけの場合でも、香典は必ず連名で記載します。あくまで夫婦で参列したいという思いを伝えるためのマナーです。こういった形で遺族に気持ちを伝えれば、特に嫌な顔をされることもありません。
喪主・喪主の妻の場合赤ちゃんはどうする?

赤ちゃんがいる状態で喪主、喪主の妻になることは、ありえなくはない事態です。そのような忙しく責任のある立場になったとき、赤ちゃんはどうするべきなのでしょうか。急に訪れて困らないためにも、対応方法を確認しておきましょう。
家族や友人に預ける
一番対応として望ましいのは、家族や友人に預けることです。家族も参列する場合は、できる限り友人に預けるようにしてください。家族に預け赤ちゃんも葬儀に参列する場合は、周囲に協力を求めながら喪主・喪主の妻の役割を行うようにしましょう。
事情を説明し赤ちゃんと参加する
どうしても預ける相手がいない場合や出産したばかりの場合は、周囲に事情を説明し、赤ちゃんと一緒に参加しましょう。このような事情があると、赤ちゃんと参列することに対して不満を抱く参列者はほとんどいません。
赤ちゃんと参加する場合でも、夫や家族、親戚としっかり相談し、協力を得ながらであれば負担も少ないです。また、あらかじめ役割を少なくしてもらい、赤ちゃんといられる時間を増やすことでも対応できます。あまり硬く考えすぎず、適度に役割をこなすようにすれば問題ありません。
一人で判断せず助けを借りながら参列しよう
赤ちゃんを連れた葬儀や葬式では、どうしても母親に負担がかかりがちです。しかし一人ではどうしても立ち行かないことも。赤ちゃんと参列するマナーを抑えながらも、一人で無理をせず家族や協力者に助けをかりながら、安心してお見送りできるよな準備を行い参列しましょう。