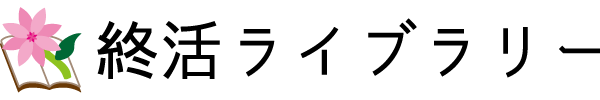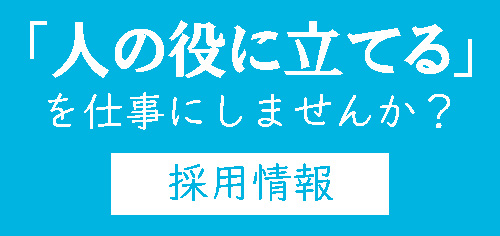お彼岸の時期にると、各お寺で合同法要が催されます。
お彼岸と言えばお墓参りですが、お墓がお寺にある場合は法要のお付き合いが重視されることもあります。
今回の記事ではお彼岸の法要について解説します。
お彼岸とは
お彼岸の法要の内容を理解するためには、お彼岸という日の意味を知っておいた方が良いでしょう。
お彼岸の意味
「彼岸」とは仏教用語で、煩悩を脱却した境地、つまり極楽浄土のことです。
「彼」は彼方(かなた)という言葉があるように何かをまたいだ遠方を指します。したがって、彼岸は何かを挟んだ向こう岸の意味です。
対して、煩悩にさいなまれる私たちがいる世界は「此岸(しがん)」と言います。
春分の日と秋分の日には、太陽が真東から真西に沈みます。
真西に沈む太陽を拝むことで、此岸から西方にある浄土に思いを馳せ、仏門の修行をするのが本来のお彼岸の意味でした。
しかし、ここに日本古来の祖先信仰が影響し、現在では故人や先祖供養の行事として広く定着しています。
お彼岸はいつのこと?
お彼岸は春と秋の2回やってきます。
お彼岸は、春分の日または秋分の日とその前後3日間を合わせた、春秋それぞれ7日間の期間のことです。
毎年の春分の日、秋分の日はそれぞれ、前年の2月1日に国立天文台が官報で発表することで、正式決定します。
2019年の春彼岸は3月18日~3月24日、秋彼岸は9月20日~9月26日です。
2020年の春彼岸は、3月17日~3月23日、秋彼岸は9月19日~9月25日です。
なお、お彼岸の初日を彼岸の入り、春分の日または秋分の日を中日、最終日を彼岸の明けと言われます。
お彼岸にすること
お彼岸は本来仏門の修行をする期間ですが、現在ではお墓参りの行事として広まっています。
お墓参り
現在では、お彼岸は先祖供養の行事として定着しているので、お墓参りに行くことが慣習となっています。
墓前に手を合わせて、故人やご先祖様にご挨拶しましょう。
また、お墓は定期的な手入れをした方がきれいなまま長持ちします。
墓石を布で磨いたり、雑草の駆除もあわせてします。
普段なかなかお参りに行けない人も、せっかくの機会なのでお墓参りに行ってみましょう。
合同法要
寺院によってはお彼岸の時に本堂で合同法要をする場合もあります。
ここに参加すれば、僧侶がまとめて読経を上げてくれるので、個人で僧侶に依頼する必要はありません。またお彼岸にまつわる法話も聞かせてもらえます。
この合同法要に出た後、自分の家のお墓参りをしましょう。
仏門の修行
お彼岸の本来の趣旨に立ち返って、仏門の修行をしてみるのもいいでしょう。
仏門の修行とは、具体的に「六波羅蜜」の実践をします。
六波羅蜜とは、浄土に行くために実践すべきことです。
以下の6つの行いが六波羅蜜です。
- 1.布施(ふせ):人に施すこと、分け与えること
- 2.持戒(じかい):教義上の生活規律を守り、反省すること
- 3.精進(しょうじん):常に努力すること
- 4.忍辱(にんにく):耐え忍ぶこと
- 5.禅定(ぜんじょう):心を落ち着かせること
- 6.智慧(ちえ):正しい判断力で真実を見る目を持つこと
お彼岸法要とは
お彼岸法要とは、お彼岸の時期に寺院で行う合同法要を指します。
お彼岸法要はどんなものなのでしょうか。
お彼岸法要ですること
お彼岸法要では、お寺の本堂で僧侶が先祖供養や仏様を讃えるために読経し、そののち法話をします。
この他、法要以外にもトークイベントなどの親しみやすい催しをあわせて開催するお寺もあります。
お彼岸法要に参列するときのマナー
お寺によっては、お彼岸の中日に「施餓鬼法要」などの合同法要が行われます。
お彼岸の合同法要に参加する時のマナーについて解説します。
お布施
お彼岸の合同法要に参加する際は、お布施を持参します。
地域やお寺にもよりますが、3,000円~10,000円を包みます。
お金は白無地の封筒に包み、水引はつけません。
表書きは、上側「御布施」、下側に指名を記載します。
お布施を渡すときはお盆に乗せて渡すのが丁寧ですが、袱紗に乗せて渡すのでも構いません。
持ち物と服装
黒やグレー、茶色を基調とした地味な服を選びます。
喪服を着る必要はありません。
持ち物は、お布施・袱紗の他は数珠を持参します。
合同法要がない・参列できないときは
特にお寺にお墓がある場合、合同法要がない、あるいは参列できないときも、お墓参りの際には寺へのあいさつをしましょう。
お墓参りだけの場合は、手土産などは不要です。
ただし、ご住職に仏事のことで相談したい、打ち合わせしたいといった場合は、手土産を持参します。
手土産は、日持ちのするお菓子が無難です。
まとめ
お彼岸には多くのお寺で合同法要が催されます。お墓参りの際、無理のない範囲で参列しましょう。
合同法要の内容は読経と法話です。
参列する際はお布施を3,000円~10,000円程度包み、持参しましょう。
特にお寺にお墓がある方は、お寺とのお付き合いを更新するいい機会です。
法話を聞く機会もそうありませんので、ぜひ足を運んでみてください。