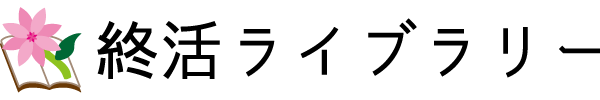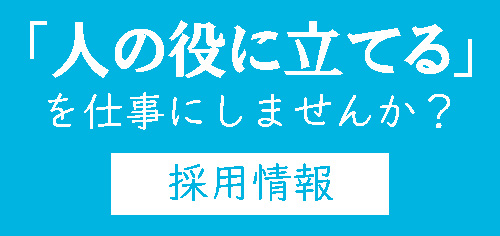葬式は故人と最後の別れをする、大切な儀式です。通夜や告別式で挨拶をするときはマナー違反をしてしまわないように、十分に気をつける必要があります。
会葬者として葬式に参列するとき、喪主となったときの挨拶については、どんなことに気をつけなくてはならないのでしょうか?マナー違反にならない、葬式での挨拶の言葉や作法をご紹介します。
葬式の挨拶で言ってはいけない言葉

死や苦しみにつながる言葉
結婚式では別れを連想させるような言葉は使わないことがマナーです。切れることを連想させるとして包丁やハサミといった刃物の名前も口にしてはいけません。
同じように、葬式でも使わないことがマナーとされている言葉があります。その一つが死や苦しみを思わせるような言葉です。
直接的な「死」や「亡くなる」、「苦しむ」、「辛い」などの言葉は、もちろん葬式で使ってはいけません。また数字の「4」や「9」も、死や苦しみを連想させるとして、使うとマナー違反になります。「消える」、「流れる」、「壊れる」といった言葉も葬式の場で口にしてはいけないワードです。
重ね言葉
「たびたび」や「またまた」という重ね言葉も、葬式の挨拶には使うことができない言葉です。同じ言葉を2回繰り返すことは、人の死という不幸なことがまた起こることを思わせるからです。
2回繰り返す言葉は重ね言葉と呼ばれ、通夜や告別式の挨拶には用いないことが常識とされています。
「ますます」や「いよいよ」、「重ね重ね」、「次々」という言葉も重ね言葉です。また動きの繰り返しを示す「再三」や「再三再四」も重ね言葉です。
重ね言葉は日常的によく使われ、葬式のさいも遺族に対して「くれぐれもお力を落とさないように」と言ってしまいがちです。「くれぐれ」も重ね言葉で、葬式では言うべきではありません。シンプルに「お力を落とさないように」と挨拶するか、「どうかお力を落とさないように」と挨拶するかにしましょう。
葬式に参列するときの挨拶のしかた

遺族への挨拶のしかた
一般的には遺族への挨拶も「このたびはご愁傷様です」や「お悔やみ申し上げます」と、短めの言葉で済ませた方がマナーにあっています。ただ遺族との関係によっては、これらの言葉だけでは冷たい印象を与えてしまうことがあるので注意しましょう。
遺族との関係が近いときは「急なことで大変でしたね」や「気落ちなさいませんように」など、遺族をねぎらったり心配したりする言葉を入れると、より良い挨拶になります。忌み言葉を使わないように注意しながら、遺族に寄り添った言葉で悲しみの気持ちを伝えるようにしましょう。
葬式の挨拶に笑顔は禁物
葬式は故人と最後のお別れをする、大切な儀式です。喪主、遺族は悲しみにくれています。参列者もきちんと哀悼の気持ちを持って、会葬することがマナーです。
遺族を元気づけようとする意図があっても、笑顔で挨拶をすることは場違いで不謹慎とみなされるので、避けるように注意しましょう。
葬式での挨拶は短めに
葬式で長くしゃべることはNG行為として、嫌われます。通夜や告別式は静かで厳かに行われるべき儀式です。いくら哀悼の念、弔辞を伝えたいと言っても、長々と挨拶することはマナー違反になるのでやめましょう。多くの参列者の対応をしなければならない喪主、遺族にとっては迷惑な行為にもなります。
特別に故人に世話になったなどで挨拶をどうしてもしたい場合には、後日に改めて弔問しましょう。
宗教の違いも理解しておく
宗教が何かによって葬式の挨拶にも違いがあります。死後の世界を指す「冥土」や、冥土までの旅路を指す「冥途」という言葉は、仏教で使う言葉です。
このため死後の世界で魂が安らかであることを祈る「ご冥福をお祈りします」という挨拶は、仏教以外の宗教ではすることはできません。葬式に参列するさいは宗教によって挨拶も違うことを理解しておくと良いでしょう。
仏教式の挨拶の注意点
日本で執り行われている葬式のほとんどは仏教式で、多くの人が葬式のマナーとして理解している作法は仏教式のものです。葬式の挨拶としてよく使われている「お悔やみを申し上げます」や「ご冥福をお祈りします」は仏教上の言葉を使った、仏教式の葬式でのみ使うことができる文言です。
しかしキリスト教で「ご冥福をお祈りします」という挨拶が使えないのと同じように、仏教でも浄土真宗の場合は「ご冥福をお祈りします」と挨拶してはいけません。浄土真宗は他の宗派とは少し違っていて、死後の魂はすぐに仏になると考えられているからです。
キリスト教式の挨拶の注意点
この世は神に生を授かったものが暮らすところで死後はもともといた場所に帰るだけという考えが、キリスト教における死の捉え方です。仏教では死後は仏になるとされているので「成仏する」という言葉が使われますが、キリスト教では「天に召される」とされます。カトリックとプロテスタントでも使う言葉が違い、カトリックの場合は「帰天する」、プロテスタントの場合は「召天する」が死ぬことの意味になります。
キリスト教にとって死は悲しいことではなく、もともといた神のもとに召されるという、どちらかと言えば喜ばしいことだという捉え方になります。挨拶にも悲しみを表現するような言葉は避け、「安らかにお眠りください」などとするのがマナーです。
神式の挨拶の注意点
死を神道では家を守る守護神になることと捉えています。神式の葬式は仏教やキリスト教のような送り出す儀式ではなく、家に留まっていただくものとして執り行われます。
神式の葬式に相応しい挨拶は、「御霊の平安をお祈りします」という文言です。しかし仏教式での「このたびはご愁傷様です」や「お悔やみ申し上げます」という挨拶を神式の葬式で使っても、マナー違反にはなりません。ただし「冥福をお祈りします」という挨拶は仏教上の言葉である冥福というワードが入っているため、神式で用いるのはマナー違反になります。
葬式で喪主をするときの挨拶のしかた

葬儀中にする喪主の挨拶のしかた
喪主として通夜や告別式で参列者全員に対して挨拶をするときにも、葬式ならではのマナーがあることに気をつけて言葉を選ぶ必要があります。参列者が受付担当者や遺族に挨拶をするときに重ね言葉や忌み言葉を言ってはいけないのと同じように、喪主の挨拶にも重ね言葉や忌み言葉を使用してはいけません。
とくに高齢の方々は重ね言葉や忌み言葉に敏感で、より不快に感じる傾向にあります。喪主の挨拶は参列者全員に向けての言葉となるので、十分に注意しましょう。
喪主の挨拶はインターネットやマナー本などで探したり、葬儀会社が用意してくれたりして、簡単に文例を見ることができます。お手本として参考にするのは良いのですが、そのまま使うのはできれば避けましょう。
挨拶は忙しい中わざわざ時間を作って故人とのお別れの場に駆けつけてくれた参列者に対して、感謝の気持ちを伝えるためにするものです。少しでもいいのでアレンジを加えて、自分の言葉で「来ていただいてありがとうございます」という気持ちを述べると良いでしょう。
喪主が挨拶でしゃべる内容
喪主の挨拶で必ず述べなくてはならない内容が、参列者への感謝です。
忙しいなか、時間を作って故人とのお別れのために駆けつけてくれた参列者に対して、喪主は遺族を代表して感謝の言葉を述べる必要があります。さらに故人の生前のエピソードを披露すると、参列者に故人との思い出が胸に刻まれるような挨拶にすることができます。
具体的には参列者に感謝の言葉を述べた後、喪主と故人との関係、故人の生い立ちや人となり、故人を特徴付けるようなエピソードの順番で語り、最後に「今後ともよろしくお願いします」という内容でまとめると、不足のない喪主の挨拶とすることができます。
僧侶への挨拶のしかたとお布施の渡し方
喪主は葬式に参列してくれた人だけでなく、僧侶にも挨拶をする必要があります。
僧侶に挨拶をしなければならないタイミングは、通夜や告別式でお経を上げるために出向いてくれた僧侶をお迎えするとき、無事に式を終えて僧侶をお見送りするときです。いずれの場合もわざわざ足を運んで、故人のためにお経を上げていただいたことに対する感謝の気持ちを挨拶できちんと表すようにしましょう。
通夜や告別式の前は「よろしくお願いします」、後では「ありがとうございました」という文言を入れた挨拶とします。僧侶に対しては持ち、丁寧に挨拶をすることが大切です。今後の法事・法要でお世話になることも多いので、良い関係を築けるように挨拶にも気を配りましょう。
お布施の渡し方
僧侶への葬式でお経を上げていただいた謝礼は、「お布施」として渡します。
お布施は通夜や告別式の前に渡す場合が多いものの、後から渡しても構いません。式の前に喪主が参列者の対応で忙しくてバタバタしている場合は、むしろ告別式や通夜が無事に終了してから落ち着いてゆっくりとお渡しする方がマナーとして好まれることもあります。
また地域によってや、僧侶との関係によってもお布施を渡すタイミングは変わってきます。分からない場合は聞いておくなど、しっかりと確認しておきましょう。トラブルになったり僧侶を不快にさせたりせずに済みます。
葬式の挨拶で気をつけること

死や苦しみにつながる言葉や重ね言葉は、葬式では使ってはいけない「忌み言葉」です。忌み言葉を挨拶で使うことは、大変な失礼をすることになります。葬式は故人と最後のお別れをする、大切な儀式です。マナー違反をしてしまわないよう、十分に注意しましょう。