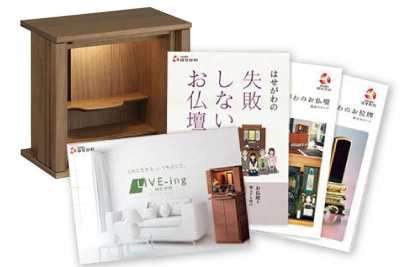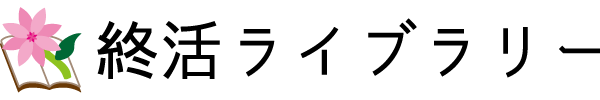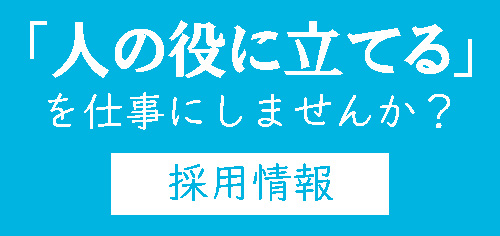お仏壇は一度購入したら代々引き継いで使用していくことが一般的です。
高いものだと100万円以上にもなりますので、購入してから後悔はしたくありません。
今回の記事では、購入前に確認しておきたいお仏壇選びのポイントを解説します。
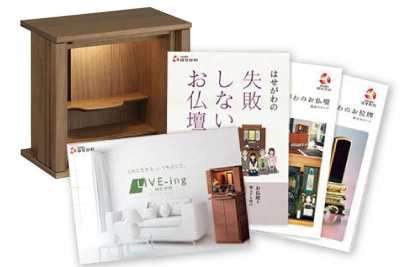
仏壇とは何か
仏壇は、自宅でお参りできるお寺の代わりになる宗教施設です。
よく「ミニチュアのお寺」とも表現されます。
仏壇はお寺の本堂を模したものなので、仏壇の中心にはその宗派で最も信仰される仏様(本尊・ほんぞん)を中心にお祀りします。
つまり、本来仏壇とは、仏様にお参りするための施設です。
しかし、位牌を祀ることからも分かるように、昨今では故人やご先祖様を供養する意味合いもあります。昨今ではこちらの認識の方が浸透しているのではないでしょうか。
位牌は故人がこの世に来る際の依り代であり、お参りする時は位牌に故人の霊を呼び出すことができます。
まとめると、仏壇は仏様や故人にお参りするための施設ということになります。
こういった仏壇の役割、あるいはどのような役割を重視するかを加味して、どのようなお仏壇が良いかを考えてみましょう。
仏壇の種類
仏壇の選び方を解説する前に、仏壇にはどのような種類があるかを紹介します。
金仏壇
金仏壇は、白木に金箔や金粉を施した仏壇です。
極楽浄土の様子を表しており、浄土真宗の方が多く使用します。
浄土真宗の中でも本願寺派、真宗大谷派で造りが異なるので、自分の宗派は事前に確認した上で購入しましょう。
メンテナンスや掃除は慎重にする必要があり、誤って金箔部分を拭いてしまうとはげてしまうことがあります。また、かえって汚れる可能性があるので素手では触らないようにします。金箔部分の扱いは特に慎重になりましょう。
唐木仏壇
黒檀や紫檀、ケヤキなどを利用した、木目調の仏壇です。
浄土真宗以外の方は基本的に唐木仏壇を使います。金仏壇と比べてシンプルな印象です。
関東と関西で違いがあり、関東の場合は全面木目ですが、関西の場合は仏壇内部を金で装飾します。
金箔部分以外は仏壇掃除用のハケで掃除することができます。
家具調仏壇
比較的新しいタイプの仏壇です。
現在の住宅で多い洋室のインテリアになじむデザインで、コンパクトなものも多く販売されています。
自宅に和室が無く、リビングに置く場合は家具調仏壇が最もなじみます。
唐木仏壇よりもさらにシンプルな構造で、掃除も比較的楽にできます。
はけを使わずとも、クロスで掃除できる仏壇も多くあります。
仏壇を選ぶ3つのポイント
それでは、お仏壇はどのように選べばいいのでしょうか。
4つの観点から解説します。
1.仏壇の置き場所・サイズで選ぶ
まずは仏壇の置き場所から考えてみましょう。
和室に置く
和室に置く場合は、伝統的な金仏壇か唐木仏壇がなじみます。
家具調仏壇はリビングの家具になじむデザインになっており、逆に和室に置くとやや違和感があります。
ただし、最近では和風テイストを意識した家具調仏壇もあるので、そちらを検討しても良いでしょう。
和室の仏壇と言えば奥にどっしりと鎮座しているイメージがありますが、必ずしも大きな「重ね型」仏壇を買う必要はなく、タンスなど家具の上に置けるコンパクトな「上置き型」などを購入しても構いません。
洋室に置く
リビングなどの洋室に仏壇を置く場合は、やはり家具調仏壇が人気です。
家具調仏壇はシンプルで色味が明るめなものが多く、目立ちすぎず、リビングの風景としてなじみます。
場所を取れない場合はタンスや棚の上に設置できるタイプもあり、バリエーションも様々です。
伝統的な仏壇よりもデザインの幅が広く、好みのものを選ぶ楽しみもあります。
置き場所のサイズ
仏壇を置く場所によって、仏壇のサイズも変わります。
仏壇を購入する前には、必ず設置場所の寸法を測っておきましょう。
仏壇のサイズは扉を閉めた状態で考えますが、置き場所の寸法とピッタリのサイズで仏壇を買ってしまうと、扉を開けることができなくなります。
ゆとりのあるサイズで仏壇を選びましょう。
なお、仏壇のサイズは「号」などで表します。
1号=約3cmで考えます。
【上置き型仏壇】
| 表記 | 高さ | 横幅 | 奥行 |
| 12号 | 38cm | 30cm | 24cm |
| 14号 | 42cm | 32cm | 25cm |
| 16号 | 49cm | 34cm | 28cm |
| 18号 | 54cm | 38cm | 32cm |
| 20号 | 60cm | 45cm | 36cm |
| 23号 | 68cm | 52cm | 40cm |
【台付き型】
| 表記 | 高さ | 横幅 | 奥行 |
| 45-18号 | 137cm | 53cm | 52cm |
| 47-16号 | 142cm | 50cm | 48cm |
| 53-18号 | 160cm | 60cm | 61cm |
金仏壇・唐木仏壇のサイズ
金仏壇や唐木仏壇が基本的に和室に置きます。
サイズに関しては、大まかに「重ね型」「地袋型」「上置き型」があります。
・重ね型
和室に一間仏間や半間仏間がある場合は重ね型の仏壇を置きます。
仏壇の下に仏具などを収納する棚がついており、便利です。
・地袋型
和室に地袋があれば地袋型の仏壇を選びます。地袋とは戸棚のようなものです。下部に棚はありませんが、小さな引き出しがついています。
・上置き型
上置き型仏壇は、棚やタンスなど家具の上に設置できるコンパクトな仏壇です。
本尊や位牌、仏具やお供えを置く最低限のスペースはあり、マンションなどスペースが取れないお家で需要があります。
家具調仏壇のサイズ
家具調仏壇は床に設置する台付き型と、家具の上における上置き型があります。
さらに形状が多様なミニ仏壇も登場しており、用途やデザインによって使い分けます。
・台付き型
リビングの床に設置する場合は台付き型を選びます。
やはり下に棚がついており、仏具などを収納できます。
・上置き型
金仏壇や唐木仏壇と同様に戸棚やタンスなどの家具の上に設置できる小さな仏壇です。やはり十分にスペースが取れないマンション暮らしの世帯などで人気です。
・ミニ仏壇
上置き型の一つとも言えますが、さらにコンパクトなミニ仏壇もあります。
箱型になっておらずプレートの上にお供えなどを載せていくタイプもあり、電材んは多様です。棚などの上にインテリアのような形で設置できます。
本来仏壇であれば本尊は必ず祀るのですが、昨今では写真や花だけを飾るものもあります。
2.仏壇の費用で選ぶ
仏壇の種類やサイズによって、費用も異なります。
予算感によってどの仏壇が買えるかを検討しましょう。
| 値段 | 種類 |
| 10万円未満 | 上置き型仏壇、ミニ仏壇 |
| 10万-30万円 | 上置き型仏壇、家具調台付き型仏壇 |
| 30万円以上 | 唐木仏壇、金仏壇 |
なお、使用する素材や技術によって、値段はかなり幅があります。
金仏壇や唐木仏壇の重ね型でも、安価なものは30万円台からありますが、高級なものになると200万円や300万円以上するものもあります。
3.自分の宗教・宗派で選ぶ
先述の通り仏壇はお寺を模した宗教施設であり、仏式の供養に用います。
どの宗派がどの仏壇を使うという厳密な決まりはありませんが、おおむね以下のような傾向があります。
浄土真宗は金仏壇
浄土真宗の仏壇は、金仏壇が多く選ばれます。
金の輝きは極楽浄土を表しており、浄土真宗が正式には金仏壇を使うとされるのはこのためです。
浄土真宗はその中でも本願寺派や真宗大谷派などいくつかの宗派に分かれており、各本山の造りを参考にしているため仏壇の形式も異なります。
浄土真宗の方は、自分の宗派まで確認しましょう。
浄土真宗以外は唐木仏壇
浄土真宗以外の宗派では唐木仏壇が多く選ばれます。
仏壇が各家庭に置かれるようになったのは江戸時代のキリシタン禁制に端を発します。
庶民がキリシタンでないことを証明するために、各家庭に仏壇が置かれるようになりました。
この時、浄土真宗以外の宗派では家に造りつけられることが多く、装飾もシンプルなものが多かったと言います。
この流れから、浄土真宗以外の仏壇は唐木仏壇で定着しました。
本尊は宗派によって違う
浄土真宗以外の仏壇は基本的に唐木仏壇ですが、お祀りする本尊は違います。
各宗派では、本尊は以下のものを選びます。
- 天台宗・浄土宗・浄土真宗…阿弥陀如来
- 真言宗…大日如来
- 臨済宗・曹洞宗…釈迦如来
- 日蓮宗…曼荼羅
なお、仏壇には本尊の左右に「脇掛け」(わきがけ)を飾ります。
脇掛けは各宗派の祖師像などを掛け軸で祀ります。
脇掛けも宗派ごとに違うので、購入する際に確認しましょう。
神道・キリスト教・無宗教の場合
仏壇は仏教の宗教施設なので、神道・キリスト教・無宗教の場合は仏壇を用意する必要がありません。
神道の場合は、神棚に仏教でいうところの位牌にあたる「霊璽(れいじ)」を置いて、故人や先祖の霊を祭ります。
キリスト教の方で家で故人を追悼したい場合は、祭壇を置きます。
祭壇には十字架や、場合によっては写真を置きます。
無宗教の方は仏壇に当たるものを設置する必要はありません。
もし何らかの形で故人を偲びたい場合は、遺影や花を飾れる手元供養品などを検討しましょう。
このタイプの手元供養品は「ミニ仏壇」として売られていることもあります。
まとめ
お仏壇は種類やサイズも豊富で、選ぶにも迷ってしまいます。
仏壇を設置する場所、予算感に合わせて、購入できる仏壇には何があるかを検討しましょう。
また、自分の信仰に合わせて、仏壇の種類を検討するのも良いでしょう。
仏壇は本尊と故人・先祖をお祀りする意味合いがありますが、自分が仏壇をどのように使っていきたいかも考えて、どんな仏壇が希望に沿うのかを考えてみましょう。