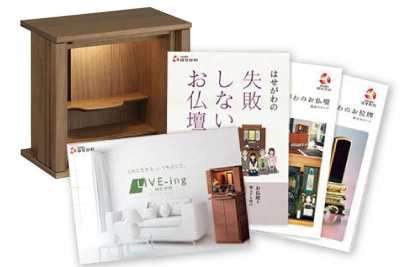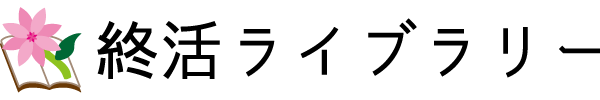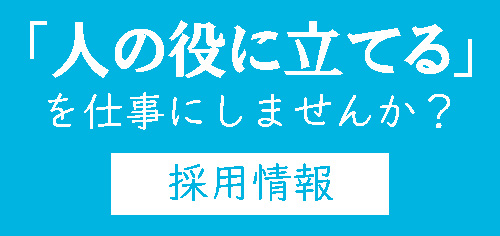近年は若い世代だけではなく、シニア世代でも死生観が変わってきて、以前のような葬儀の方法や、祖先の供養方法にそれほどの意味を見出さない人が増えてきました。
その1つの表れが、仏壇の扱い方です。仏壇は結構な場所を取りますので、そこに意味を見出せないと邪魔になるばかりです。特に昔の人は大きな仏壇を用意していましたから、それをそのまま承継した場合は、扱いに困るでしょう。
そのような場合には処分しても良いのでしょうか。
また処分する場合はどのような方法を取ればよいのでしょうか。
そこでここでは仏壇を飾る意味を今一度明らかにし、それでも処分したいという場合にはどうしたらよいのか、という点について解説します。
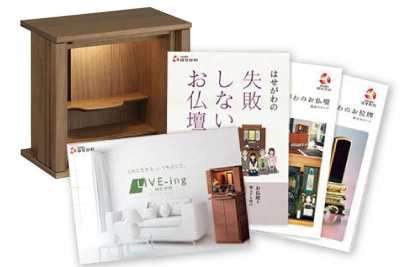
仏壇を置く意味は何か
まず最初に仏壇の意味です。本当に仏壇は置く意味があるのでしょうか。
仏壇とは何か?
仏壇とは何かということを一口で言うと「自宅のお寺」です。
お寺にお参りしたいと思うとあえて外に出なければならないうえ、近くに菩提寺が無ければお参りの足も遠のいてしまいます。
仏壇は、足繁くお寺に行く代わりに、実家のお寺としてお参りするために設置します。
ですから仏壇にはお寺と同様に本尊が必要です。
本尊は宗派によって阿弥陀如来や大日如来など異なりますが、どの宗派でも共通しているのは、仏壇の中の一段高い「須弥壇」に本尊を祀り、その下に自分の先祖の位牌を安置するということです。
この形式も本物のお寺と同じです。
仏壇を置く意味とは?
では仏壇は本当に必要なのでしょうか。
家に置いて、ある程度の場所を用意しなければならない理由は何なのでしょうか。
その理由は以下のようなものです。
精神的な支えになる
現代人は仕事やプライベートの面で大きなストレスを抱えていることが多いです。
ストレスの解消方法としては趣味やスポーツ、あるいは休息などがありますが、しかしそれらは言ってみれば対処療法で、ストレスが溜まらないという仕組みではありません。
一方で現代人は物質的には大いに恵まれています。
しかし不思議なことに、物質的に恵まれてるほど、精神的には渇望状態になることが多いのです。
そのような場合に健やかに生きていくために効果的なのが宗教です。
宗教は心のありようを変えてくれますから、ものの考え方が変わるので、そもそもストレスを感じにくくなります。
また精神的に満たされるため、物質で満たされなかった心の隙間を埋めてくれます。
ですからどのような宗教でも自分のフィーリングに合っていれば良いのですが、その中でもおすすめは実は仏教です。
仏教は日本人の性格に合わせて発展してきているので、日本人には非常に適している宗教なのです。また新興宗教などでなければ、お布施を強要されることや理不尽な修行をさせられるということもありません。
それに加えて、本尊だけではなく、自分の家族も仏教によって祀られているので、安心感があります。
その仏教に帰依する際に、家に置いておくとすぐにお参りができて便利なのが仏壇なのです。
先祖に感謝することができる
考えてみれば当然ですが、なかなか気づかないことが、自分はどこか無の世界から突然生まれた生物ではないという点です。
自分が生まれるためには両親が必要ですし、両親が生まれるためには祖父母が必要ですし、祖父母が生まれるためにはその祖先が必要です。
つまり自分がいまここに存在しているのは、そのような古来より営々と繋がっている先祖がいたからこそのことなのです。
自分が存在し、おいしいものを食べ、やりがいのある仕事をし、家族と幸せに暮らしていられるのは、その意味では全て先祖のおかげなのです。
そう考えると祖先に感謝をしたいという気持ちになりませんか。
その気持ちを行動で表すことが供養です。
仏壇が家にあるとそのような先祖供養も毎日手軽にできるのです。供養と言っても難しいことではありません。毎朝仏壇に手を合わせ、線香や供物をあげることだけで十分です。
亡くなった家族と対話できる
特に宗教に帰依していない人でも、自分が困難な場面にぶつかった時、あるいは物事が決められなくて悩んでいる時に、大切にしてくれた祖父母や両親などに心の中で問いかけたりすることはありませんか。
あるいは新しいことに挑戦する時にも、亡くなった両親などに守ってくれるように頼むかもしれません。
これは長い歴史で先祖を祀ってきた日本人としては多くみられる精神構造でしょう。
そのような時に、何も場所や機会がないとなかなか故人に話しかけたり、問いかけたりすることができないでしょう。
しかし仏壇があれば、1日に1回仏壇に向かって心の中で話しかけることで、亡くなった家族と対話ができ、それは結果的に自分を励ましたり、安心させたり、精神的に安定させたりすることに繋がるのです。
ですので仏壇があることで亡くなった家族と対話ができるということも仏壇を家に置く意味なのです。
なぜ仏壇を置くようになったのか?
仏教の伝来は6世紀中盤の飛鳥時代でしから、今から約1500年前です。
この時代に国宝の「玉虫厨子(たまむしのずし)」が作られ、それは日本史の教科書の口絵写真などで見たことがあるかもしれません。
この玉虫厨子は実は仏壇なので、この時代には既に日本では仏壇が作られていた、ということが定説です。
その後貴族などの特権階級だけが、それこそ自宅にお寺を建てる代わりに、自宅に仏壇を安置して、お参りのために、あるいは自分が亡くなったあとに極楽に行けるために、祈っていました。
さらに時代が下って、江戸時代になって「寺請制度(てらうけせいど)」という、全ての日本人はどこかのお寺の所属しなければならないという制度が導入されたことで、庶民の家にも仏壇が設置されるようになりました。
仏壇は必要か?いらない理由は?
以上のように仏壇を家に置くことには多くの効用がありますが、しかし仏壇を置きたくない人には置きたくない理由があります。
それは主にはどういう理由なのでしょうか。
仏壇が不要な理由は?
仏壇が家にあると、仏様や故人、先祖を思うことで、気持ちの支えになります。
しかし本質的に言えば、大切なのは形ではなく、故人を供養したいという気持ちです。
ですからその気持ちさえあれば、仏壇の代わりに、本棚の隅に自分の守り本尊のお札を貼ったり、故人の写真を飾ったりして、その前で毎日対話をすれば、それで十分なのです。
その意味では仏壇は絶対に必要なものではありません。
無宗教なら仏壇は不要?
またそもそも、仏教を信じていないという場合は仏壇は不要です。
しかしその場合は、毎日押し寄せるストレスを自分で対処するための何らかの方策を考えなければならないでしょう。
それもモノによっては本当の意味で人は救われません。
ストレスも悩みも根幹は精神の世界で起こっていることで。したがってモノではなく、ココロとして自分の救いになる何物かを見つける必要があります。
浄土真宗での仏壇の位置づけ
仏教でも浄土真宗における仏壇は、故人を祀るというよりは、本尊を祀るといった意味合いが強くなります。
仏壇の仏教上の機能は、極楽から先祖や故人の霊が降りてくる際のよりどころであり、あるいは信じている仏とのコミュニケーションの場です。
しかし浄土真宗の場合は、故人は亡くなった瞬間に阿弥陀如来が極楽に導いて成仏させてくれるので、この世に降りて来るということはありません。
したがって、本来仏壇に向き合って故人とコミュニケーションをとるということはしません。
したがって、浄土真宗では故人の依り代となる位牌は作りません。
先祖の記録は、「過去帳」に記録されます。
いらない仏壇はどうすればいい?
以上のように信仰自体は持っていたほうが良いと言えますが、しかし仏壇という形は絶対的に必要なものではありません。
にもかかわらず、親などが亡くなって実家にあった大きな仏壇を引き継がなければならなくなった、という場合もあるでしょう。
そのような時にはどうしたらよいのでしょうか。
実家の仏壇を処分するには?
最も簡単な方法は、仏壇を処分してしまうことです。
しかし先ほど書いたように、仏壇は故人の霊が降りて来る依り代です。
依り代ということは、仏壇はあの世から見ると、まるでバス停のように、降りて来る場所として認識されています。
したがって、その認識をされたままの状態で処分するわけにいきません。
ですから、仏壇を処分する際には、その認識を取り消して、あの世から仏壇を見えなくしてしまうことが大切です。
そのために行うことが閉眼供養です。
閉眼供養は僧侶を自宅に招いて読経をあげてもらえばOKです。
その閉眼供養さえしてしまえば、その後の仏壇は唯の大きな木の箱なので、どのように処分しても大丈夫です。
ただしこれは現世の話になりますが、仏壇は大きいので普通ゴミとしては出せず、粗大ゴミになることに注意しましょう。
自宅に作業スペースがあって工具が用意できるなら、仏壇を解体して1枚1枚の板にしてすれば普通ゴミとしても出せます。
粗大ゴミとして出すのも大変だし、ましてや仏壇を解体することなど不可能、という場合には仏壇を処分してくれる専門の業者に頼みましょう。
寺院が請け負っていることもあります。そのような業者に頼むと、仏壇の処分だけではなく、その前の閉眼供養もしてくれるので、全て任せられます。
その際の費用の相場は、まず閉眼供養だけを寺院に頼んだ場合はお布施として1万~5万円が必要です。
これにお車代として5000円程度を別の封筒で用意しましょう。
さらに仏壇を清らかな火で燃やしてくれる「お焚き上げ」も頼むと5000円~1万円の費用がかかります。
以上を専門業者に頼んだ場合、トータルで3万円程度でしてくれるでしょう。
仏壇の代わりになるものは?ミニ仏壇など
また中には引き継いだ仏壇自体は大きくて場所を取るので自宅には置けないが、故人にお参りする場所は自宅に確保したいという場合には、手元供養をしたりミニ仏壇を用意するということも選択肢になります。
手元供養とはその名の通り、自分の身近に故人の遺骨を置き、日々供養するものです。手元に置く方法も、テーブルの上に乗るミニ仏壇などを購入して、そこに遺骨の一部を納めたミニ骨壺を安置することも可能です。
さらには遺骨を加工してペンダントにし、常に身に着けているという方法もあります。
まとめ
仏壇を家に置く意味がお分かりいただけたでしょうか。
しかし仏壇を家に置く本当の理由は非常に精神的なものです。
したがって仏壇という形にこだわる必要は必ずしもありません。
の場合には仏壇を処分して、あとは手元供養で故人を祀ってもよいでしょう。