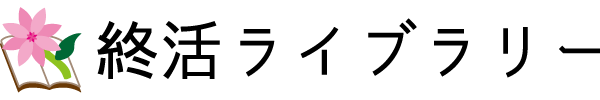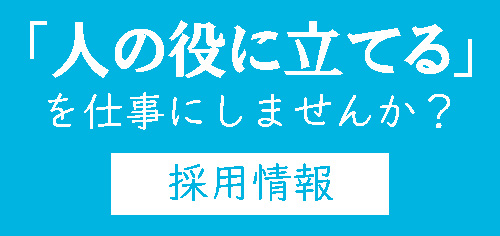近年では葬送の多様化が進み、終活という言葉もよく耳にするようになりました。
終活とは「人生の終わりのために行う活動」のことです。
安心して余生を過ごすために、終活を行ってみませんか?
この記事では終活について、いつから何をすればいいかを解説します。
終活とは
人生の終わりのために行う活動、これを略して終活と呼びます。
2010年の新語・流行語大賞ノミネートをきっかけに、終活という言葉が広く使われるようになりました。
終活の中には昔から行われている物もありますが、終活という言葉が広まると共に、その内容も時代に合わせ最適化されてきています。
以下では終活の意義や目的について解説します。
終活の意義
終活を行う意義は、身体・精神が健全なうちから人生の終わりについて考えることにあります。
いざとなってからでは遅いことを、健全なうちから準備する、人生の保険だと考えてよいでしょう。
認知症などで老後に意思表示をできなくなる場合もそうですが、事故などに合い、意思表示をすることが難しくなった場合に備えて若くから行う場合もあります。
終活の基本的な目的
終活の基本的な目的は、自分の死と向き合うことです。
自分の死後について考え、残された家族や、友人・知人についても考える。
これが終活の基本的な目的です。
終活のメリット
終活を行うことにはたくさんのメリットがあります。
その中でも代表的な物を紹介します。
精神的に安心できる
急な葬儀で慌てて帰省をした経験がある方は多いのではないでしょうか。
どんな葬儀を行えばいいか、参列者は誰を呼ぶべきか、突然の事だと残された家族の負担は大きくなります。
事前に終活を行うことで、家族の負担を減らし、結果的にご自身も安心して生活を送れるようになります。
人生の目標ができる
終活を行うことで、自分に残された時間や、これからの人生について深く考えることができます。
いままでの人生でやり残したことはないか、これからの人生をどう過ごすか。
これらを考えることで、新たに目標が生まれ、豊かな人生を過ごすことができます。
終活のデメリット
人生の終わりについて考える、こう聞くと暗く不安な気持ちになってしまうことがあります。
ご自身が不安そうに終活を行っていれば、家族も不安になってしまいます。
余計な不安を感じることで、終活を行うこと自体がデメリットとなる場合があります。
終活を行う前にしっかりと心構えをし、事前に家族に相談をすることで、終活自体がデメリットになることを防ぐことができます。
終活をいつから始めるか
終活を始める時期に決まりはなく、人によって様々です。
いつから始めるべきか悩む方も多く、始める前に挫折してしまう場合もあります。
そこで実際に終活を始めた方の意見や、アンケート結果などを元に、終活をいつから始めるべきか解説をしますので参考にしてみてください。
定年退職など人生の区切り
退職後はご自身で使える時間が増え、終活に取り組む時間を作りやすくなります。
退職後の余生についてじっくりと考えることで、やり残したことなどをなくし、充実した余生を過ごすことができます。
親族の葬儀をきっかけに、終活を始める方もいます。
身近で実際に葬儀などを体験することで、自分はこうしたい、こんな苦労を家族にはかけたくないなどの思いがきっかけになります。
いつから始めてもいい:思い立った時が最適
終活を始める時期に決まりはありません、早ければ早いほどじっくりと考え、その後の人生を豊かに過ごすことができます。
終活として行えることは多様で、その分時間もかかります。
思い立った時に始めてしまうことが最適なのではないでしょうか。
男性の終活の意向者は20代よりも50代の方が少ない
楽天インサイトで行われた調査で、終活の意向者の内訳は以下のようになります。
・男性
20代6.4% 30代7.7% 40代10.7% 50代5.9% 60代10.7%
・女性
20代5.9% 30代10.% 40代13.3% 50代13.8% 60代15.6%
全体的に女性よりも男性の方が少なく、男性の場合は20代よりも50代の方が少ないという結果でした。
終活で行うこと
終活で行うことは、自分1人で今すぐ始められることから、家族と相談しながら進めることまで多様です。
以下では終活で行う代表的な物と、終活の進め方について解説をします。
終活の進め方
終活の進め方について、一般的に行われている事を順に解説します。
終活の行い方に決まりはなく、必ずこの順番を守らなければならないわけでもありません。
この記事を参考に、手を付けやすい物や、気になった物から始めてみましょう。
家族や友人に終活を行うことを伝える
1人で終活を行うこともできますが、中には家族の協力が必要な物もあります。
事前に終活を行うことを伝えることで、その後の終活をスムーズに進められます。
家族に何も伝えないまま終活を始めると、余計な不信感や不安を与えてしまう場合もあります。
ある日突然お墓を探し始め、遺書を書き始める。
何も知らなければ、重病にかかってしまったのでは・・・と家族に心配されてしまう場合もあります。
残りの人生について考える
自分に残された時間を知ることで、残りの人生でできること・できないことを判断できます。
終活には時間がかかる物もあるため、残りの時間を把握することは重要です。
身の回りの物を整理する
遺品の整理は、家族にとって大きな負担となります。
持ち主が不在な状態では、大切な物を判断することは難しく、思い入れのある物や高価な物が捨てられてしまう場合もあります。
ご自身が健在なうちに、身の回りの物を整理することで、残された家族の負担を大幅に軽減できます。
お墓・葬儀の準備をする
生前にお墓や葬儀の準備をしておくことで、家族の負担を軽減できます。
ご自身の好みを反映したお墓を建てることや、自然に還るために散骨を行うなど、家族の判断だけでは難しいことも、終活を行うことで可能になります。
ご自身の宗派や、予算を事前に確認し、お墓を建てる場合は継承者を決めておくことも重要です。
エンディングノート・遺書を用意する
終活で準備したことなどを書き記すことで、正確に家族に情報を伝えることができます。
エンディングノートを活用することで、スケジュール管理を容易に行えます。
エンディングノートを見直すことで、不足していることや工夫できる物を新たに発見することもできます。
エンディングノートとは
エンディングノートとは、終活で行ったことや、今後行おうと考えていることを書き記すための物です。
ご自身の考えをまとめ、終活を進めやすくし、死後に家族へご自身の考えを伝える役目もあります。
エンディングノートの種類は様々で、自分で作成することもできます。
書店で販売している物や、寺院や霊園などが配布している物もあります。
使いやすさ、家族への情報の伝えやすさなどを考慮し、実際に見比べてみることをおすすめします。
遺書・遺言書・エンディングノートの違い
遺書とエンディングノートは共通している部分があり、書き方も自由です。
遺言書は法的拘束力を持ち、決まりに従って書かなければ効果がありません。
それぞれをしっかりと区別し、使い分けることが重要です。
それぞれの特徴を解説します。
遺書
遺書は死後に言い残す言葉を書き記したものです。
書き方に決まりはなく、メールや簡単なメモ書き程度でも遺書になります。
遺書には法的拘束力がなく、財産分与などについて書いた場合でも、ご自身の意見が反映されるとは限りません。
遺言書
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺書やエンディングノートとは違い、法的拘束力を持っているため、財産分与などに関して遺族は遺言書に従う必要があります。
書き方には決まりがあり、書き間違えや曖昧な表現があった場合は、無効とされるため注意が必要です。
エンディングノート
エンディングノートには死後のことに限らず、残りの人生について様々なことを記入します。
財産のことや、お墓のことなどご自身の希望を書くことはできますが、必ずその通りになるとは限りません。
そのため、財産分与に関してエンディングノートとは別に遺言書を容易する必要があります。
独身・おひとり様の終活
独身・おひとり様の場合の終活は、少し違った物になります。
死後のことについて考えるよりも、老後について考え準備することが多く、こちらがメインになります。
体が衰え、日常生活が難しくなった場合はどうするのか、その場合に頼れる人は居るのか。
頼れる人が居ない場合は、福祉制度に頼ることになります。
高齢化が進み、介護士・民生委員は人手不足です。
いざ必要になってからでは、十分なサービスが受けられない場合があり、自分の意志がきちんと伝えられない可能性もあります。
健全なうちから行動し、しっかりと準備をすることで安心して老後を迎える。
これが独身・おひとり様が終活を行う上で重要な目的です。
まとめ
終活とは、人生の終わりのために行う活動のことです。
身体・精神が健全なうちから人生の終わりについて考え、準備をすることで安心して老後を迎えることができます。
ご自身だけではなく、残された家族の負担を軽減することにも繋がります。
終活を始める時期に決まりはありません。
早くから終活を行うことで、より充実した人生を過ごすことができます。
終活で行う基本的な事は、残りの人生について考える・お墓や葬儀の準備・エンディングノートを書く、この3点です
独身・おひとり様の終活は、死後のことよりも、老後の事を重点的に考え準備をします。
老後に十分な福祉サービスを受けるために、より早くから終活を行う必要があります。
以上、終活についての解説でした。