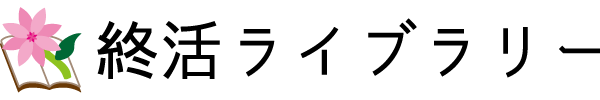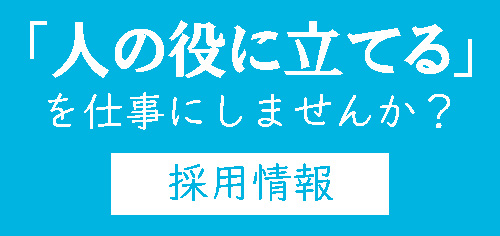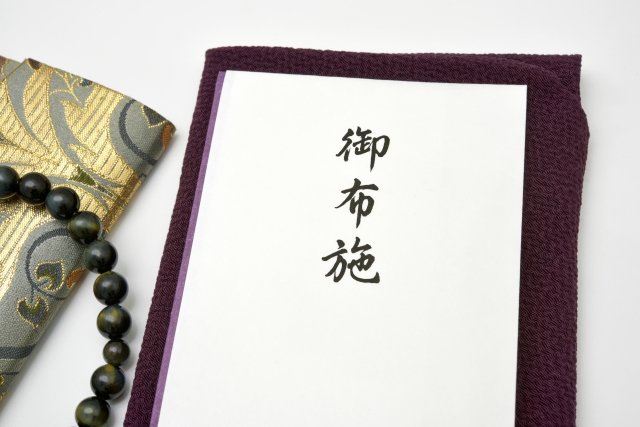
仏式の葬儀をする場合、僧侶にお布施を用意します。
僧侶は、通夜、告別式、式中初七日法要などで読経をしてもらいます。
また、戒名を頂くのにもお布施が必要です。
今回の記事では、お布施の相場や渡し方について解説します。
葬儀のお布施の内訳
葬儀のお布施は、大きく以下の2つに分かれます。
- 通夜、告別式での読経
- 戒名のお布施
それぞれ別々に包んで渡す必要があるので、それぞれの相場を知っている必要があります。
葬儀のお布施の相場
日本消費者協会の調査によると、 2017年時点でお布施の平均金額は47.3万円でした。
ただし、当該の調査ではサンプル数が少ないため、あくまで参考値です。
(参考:葬儀業界の現状 7. 葬儀費用の紹介(全国・関東B) )
それでは、お経料と戒名料はどれぞれどれくらいで用意すればいいのでしょうか。
お経料の相場
お通夜、告別式の2日間でお経をあげてもらった場合は、10~30万円ほどが相場です。
ただし、お寺の寺格や地域、付き合いの長さによって相場となる金額は変わります。事前に葬儀社やお寺に相場感を聞いておくのが確実です。
戒名料の相場
戒名料は、20~50万円程が相場です。
ただし、戒名料は、戒名のランクによって幅広く変わります。
さらに、お経料と同様寺格や地域によっても異なります。
戒名のランクについて少し解説します。
戒名とは仏弟子になったことを示す名前で、本来は二文字です。
これに院号、道号、位号が加わった7文字~12文字のものを、今日では広い意味で戒名と言います。
例えば、戒名の一番最後に付ける位号で考えてみましょう。
もっとも位の低い「信士」「信女」であれば5~20万円程、最高位の「院信士」「院居士」などを付ける場合は50~100万円以上にもなります。
さらに、戒名の最初に来る院号を足すと、さらに高額なお布施が必要になります。
葬儀のお布施の渡し方
それでは、用意したお布施はどのように渡せばいいのでしょうか。
渡し方について解説します。
誰にいつ渡す?
お布施は来ていただいた僧侶に直接渡します。
タイミングは、お葬式が始まる前のあいさつに伺うときです。
他の葬祭費用は葬儀終了後、葬儀社に支払うので、混同しないように注意しましょう。
お布施の包み方
お布施の包み方について解説します。
封筒と表書き
お布施は市販されている白無地の封筒に入れます。
郵便番号欄が印字されていないものを選びましょう。なお、水引はつけません。
また、表書きがすでに印刷されている封筒を使っても構いません。
表書きは、お経料は「御布施」、戒名料は「戒名料」として、その下に施主の名前を書きます。
お経料と戒名料をまとめて渡す場合は「御布施」とし、お渡しする際に戒名料も含まれていることを一言添えましょう。
なお、正式には奉書紙で包むのが正式とされていますが、一般的には封筒を使う方が多いようです。
中袋の書き方
中袋には金額と住所・氏名を書きます。
金額は表面中央または裏面右側に書きます。
金額は旧字体で書きましょう。
【旧字体参照】
一:壱
二:弐
三:参
四:四
五:伍
六:六
七:七
八:八
九:九
十:拾
百:佰
千:阡
万:萬
円:圓
お金の入れ方
お金は、お札の表面(人物の肖像画がある方)が封筒の表面側、かつ、ふた側に来るように入れます。
全てのお札の向きがそろっていることを確認しましょう。
なお、香典はお札の表面が封筒の裏側に来るように入れるため、混同しないようにしましょう。
香典は弔事の際の包み方をしますが、お布施は僧侶に不幸があったわけではないので、慶事の包み方をします。
お布施の渡し方
お布施は直接手渡しにはしません。
渡し方は、切手盆と呼ばれる小さなお盆にお布施をのせたり、袱紗(ふくさ)の上にお布施を置いて渡します。
切手盆は葬儀社が貸してくれることもあるので、相談してみましょう。
袱紗で渡す場合は、渡す直前に袱紗を開き、お布施を袱紗の上にのせて渡します。
袱紗の色は、弔事の時は紫、紺、緑、グレーなどが良いとされています。
紫の袱紗は慶事でも使えるので、1つ持っておいて良いでしょう。
お渡しする際は「本日はよろしくお願いします」や「本日は、○○の供養をいただきありがとうございました」などと一言添えるといいでしょう。
その他の法要のお布施
葬儀が終わると、回忌法要や年忌法要の際にも僧侶を呼んで供養してもらいます。
参考までに、その時のお布施についても紹介しておきます。
- 回忌法要・年忌法要:3-5万円
- 祥月命日:5,000円-1万円
- お盆に来ていただいたとき:5,000円-1万円
- お盆・彼岸の合同法要:3,000円-1万円
- 納骨法要:1-3万円
葬儀が終わったらまずご遺族は心身ともに休息をとることが最優先ですが、少し落ち着いたら四十九日の準備も始めましょう。
まとめ
葬儀のお布施の相場は全国平均で44.7万円(お経料、戒名料込)です。ただし、参考値としてとどめてください。
実際には地域や寺格、付き合いの長さによって変わるので、お寺や葬儀社に相談しておくのが良いでしょう。
包むものは白無地の封筒で、水引はつけません。
お布施は葬儀前に僧侶に挨拶するタイミングで渡します。
手渡しではなく、切手盆や袱紗を使いましょう。