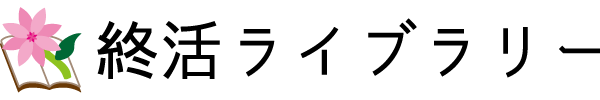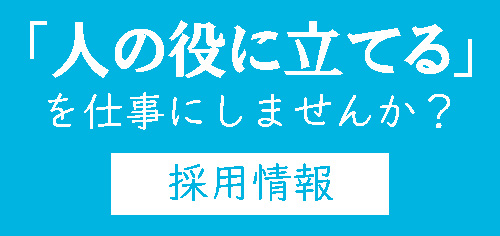近親者が亡くなったとき、葬儀で喪主を務めたり、遠方の葬儀に参列したりするために会社や学校を休まなければならなくなることがあります。そのために取ることができる特別休暇を「忌引き」といいます。
訃報はいつ来るかわかりません。その時、まず会社や学校に連絡し、忌引き休暇の申請をしなければなりません。
いざというときに慌てることがないよう、忌引き休暇の日数や取り方などについてまとめました。
忌引き休暇の制度は企業や学校で違う
実は忌引き休暇については労働基準法などによる規定がありません。企業であれば就業規則などで定められているため、企業や学校によって違っています。忌引きで休むことができない企業もありますが、違法にはなりません。
大半の企業では忌引きの休暇を取り入れています。企業によっては「忌引き休暇」ではなく「慶弔休暇」としている場合もあります。
ただ、その内容はさまざまで、忌引き休暇であっても有給とは限りません。就業規則に「無給とする」という規定があれば、休む権利があるというだけということになります。正社員と契約社員・アルバイトで違う場合もありますので、確認が必要です。
学校では、忌引き休暇の期間は一般的な「欠席」になりません。「出席」という扱いにもならず、進級のために必要な日数から忌引きの日数が引かれます。
忌引き休暇の日数は?
通常、故人との血縁関係によって長さが変わります。企業によって違いはありますが、以下に一般的な例を挙げます。
- 配偶者:10日間
- 父母:7日間
- 子:5日間
- 祖父母:3日間
- 兄弟姉妹:3日間
- 孫:1日間
- 叔父叔母:1日間
- 配偶者の父母:3日間
- 配偶者の祖父母:1日間
- 配偶者の兄弟:1日間
遠方での葬儀の場合、往復に要した日数を忌引きに含める企業もあります。
いつから忌引き休暇とするかについては、亡くなった日もしくは翌日から起算するのが一般的ですが、最近は亡くなってから通夜・葬儀の日まで日数を要することがあるため、死亡日もしくは通夜を起算日とする企業もあります。
忌引き休暇を取る際のマナーと注意点
忌引き休暇の連絡はなるべく早く
忌引き休暇を取るときは、なるべく早く伝えるようにしましょう。会社員であれば上司に、学校であれば担任の先生に伝えます。忌引きに関する書類を提出しなくてもよい場合、まず口頭で伝え、その後メールで詳細を伝えるのがマナーです。
亡くなった方についてはできるだけ具体的に伝える必要があります。たとえば、「祖父」でも自身の祖父か、配偶者の祖父かによって取得する日数が変わるからです。また、自身が喪主であるかどうかも伝えます。
会社の関係者や学校の先生などが参列することもあるため、通夜・告別式の日時や場所も伝えるようにしましょう。
正確に業務の引き継ぎを
身近な家族が亡くなったときは忌引き休暇も長くなり、その間の業務を引き継いでもらうことになります。
慌ただしい事情の中であっても、自分の代理で業務をお願いすることになるので十分な配慮が必要です。業務内容や取り付けているアポイントを伝え、業務が滞ることのないよう引継ぎを行いましょう。
また、緊急の場合に連絡が取れるよう、プライベートの電話番号を伝えておくようにしましょう。
忌引き明けのマナー
忌引きで休暇を取った場合、規則で認められていることとはいえ、急な休みで周囲の人に迷惑をかけたり、協力してもらったりしています。
休暇が明けて出社したときには、まず上司や同僚に挨拶をして、感謝の気持ちを伝えましょう。香典をいただいている場合には香典返しを渡します。忌引きが長期になった場合、菓子折りを持参する方もいるようです。
まずは就業規則の確認を
忌引き休暇の制度は企業によって違います。日数や起算日、有給か否か、正社員か契約社員・アルバイトによる違いがあるかといった事項のほか、訃報や礼状の提出を求められる場合もあります。
いざというときに慌てたり、トラブルになったりしないよう、就業規則を見直し、総務担当者などに確認しておきましょう。