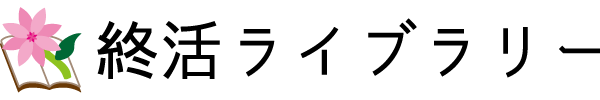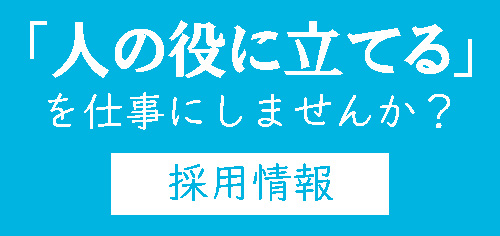葬儀には、喪主と施主がいます。個人葬では、喪主と施主が兼任することが多いため、混同されることが多いようですが、別々の人を立てて良いのです。
喪主と施主の違い
喪主と施主についてそれぞれ解説します。
喪主とは?
喪主とは、喪家の代表者として葬儀を取り仕切る人です。
葬儀に関する決定の最終責任者であり、また、葬儀社、お寺、参列者など各方面の対応窓口になります。
仕事内容としては、葬儀社との打ち合わせ、お寺への挨拶、参列者への挨拶、お葬式でのあいさつなどをします。
施主とは?
施主とは、葬祭費用を負担する人です。
複数人で費用負担を分担する場合は、それを取りまとめる代表者が施主になります。ただしこの場合、あえて施主を立てなくても構いません。
施主とは、「布施する主」という意味です。
喪主と施主は違う人?
それでは、喪主と施主は違う人が務めるのでしょうか。
現代において、喪主と施主はおおむね同じ人がやるようです。
つまり、1人の人が葬祭費用を取りまとめ、葬儀の取り仕切りもするということです。
ただし、葬儀を実際に取り仕切る人と費用負担をする人が異なれば、喪主と施主は違う人になります。
例えば、以下のような場合です。
- 配偶者が喪主で、費用負担は子供がする
- 社葬で、遺族が喪主を務めるが、費用は会社が負担する場合
喪主と施主の決め方
喪主・施主ともに、故人と血縁関係の深い順に決めていくのが一般的です。
ほとんどの場合で故人の配偶者や子供が喪主や施主になります。
また、子どもの中では長男が喪主となるのが一般的と言えます。
これは、「祭祀承継者」が長男となることが多いからです。
祭祀承継者とは「祭祀財産」を故人から承継する人のことで、「祭祀財産」とはお墓や仏壇・仏具、系譜など、その家の祭祀に関わる財産のことです。
祭祀承継者は故人の指定があれば誰でもなることができますが、慣習の面から言えばいまだに長男がなることが多いでしょう。
祭祀財産については、民法の第897条に規定されています。
参考:e-Gov 民法 第八百九十七条
なお、親より子どもが先に亡くなった場合は「逆縁」といい、かつては親は喪主を務めないという風習がありました。
ですが、現在では逆縁の場合でも親が喪主をつとめることは珍しくありません。
喪主と施主の仕事内容
それでは、具体的に喪主と施主はそれぞれどんな仕事内容があるのでしょうか。
喪主の仕事内容
繰り返しになりますが、喪主は葬儀全体の取り仕切りや決定をする人です。
具体的には、以下のような仕事があります。
- 訃報を出す
- 葬儀社との打ち合わせをする
- 遺族間での仕事分担を決める
- 僧侶の手配と僧侶への挨拶をする
- 参列者の座席を決める
- 供花の配置を決める
- 弔電の順番を決める
- 会葬者に挨拶をする
- 出棺前の挨拶をする
- 精進落としの挨拶をする
- 葬儀後に香典返しを送る など
喪主は葬儀でもっとも大変なポジションなので、兄弟や子どもがサポートし、仕事を分担しましょう。
施主の仕事内容
施主としての役割は金銭を負担することです。
その他は、喪主のサポートに徹します。
葬儀の挨拶はどちらする?
出棺前の挨拶や精進落としの挨拶は喪主がします。
お布施はどちらが僧侶に渡す?
僧侶にお布施を渡すのは、葬儀前にご挨拶に伺うタイミングです。
僧侶への挨拶は喪主が行うので、お布施も喪主が渡します。
喪主と施主は香典を用意する?
施主は葬儀の費用負担をしているため、香典を自分で包むことはしません。
喪主も葬祭費用を負担しているのであれば当然包む必要はありませんが、喪主と施主が違う人で、喪主が一切の費用負担をしていなければ、施主に香典を包むこともあります。
喪主と施主は供花を出す?
必ずではありませんが、喪主や施主が供花を出すこともあります。
名義は「親族一同」や「施主」などとします。
地域などにもよるので、分からなければ葬儀社に相談しましょう。
弔電は喪主と施主どちらに打つ?
喪主が葬儀の代表者になるので、弔電は喪主宛てに打ちます。
まとめ
喪主は葬儀の実際の取り仕切りや決定、施主は葬儀の費用負担をする人です。
現代ではおおむね同じ人が喪主と施主を兼任しますが、親が葬祭費用を出して子供が葬儀を取り仕切るといった場合は、喪主と施主は別な人になります。
実務的な面で言えば喪主が葬儀中は最も忙しいので、施主を含めた遺族は仕事を分担してサポートしましょう。