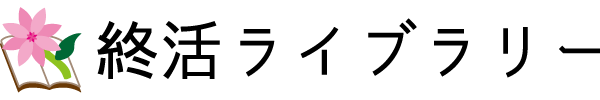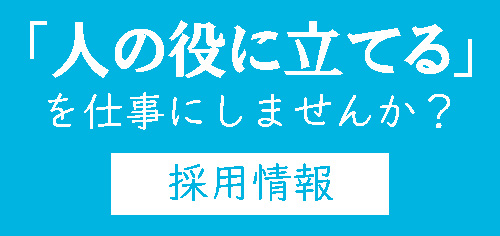高齢期を迎えるうえで避けて通れない介護の問題。その時お世話になるのが介護保険です。
かつて、高齢者の介護は家族が担ってきました。しかし、少子高齢化・核家族化・独身者の増加などのために家族だけでは負担できなくなり、「介護の社会化」が求められるようになりました。
これに対応して平成12年に導入されたのが介護保険制度です。
介護保険とはどのようなものなのか、実際に利用するにはどうすればいいのかをまとめました。
介護保険の仕組みは?
介護保険制度は、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者に介護サービスを提供する制度です。40歳以上の国民すべてが加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
制度の運営主体は、国民保険と同じく市町村および特別区で、ある程度の自由な裁量に任されています。そのため、市区町村によってサービスの種類や利用限度額が異なり、その内容は条例によって定められています。
被保険者は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に区分されます。
第1号被保険者は、介護が必要な状態になると、その原因がどういうものであっても、認定を受けて介護サービスを受けることが可能です。
第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など「介護保険法」に定められた16の特定疾病が原因で介護が必要になったときのみ、認定を受けて介護サービスを受けられます。
介護保険制度の財源は公費(税金)が50%、保険料が50%です。第1号被保険者の保険料は年金から天引きされ、第2号被保険者の保険料は加入している医療保険料に加算されます。給与所得者の場合、他の社会保険料とともに天引きされます。
65歳になると、市区町村から「介護保険被保険者証(保険証)」が交付されます。介護保険サービスを受けるにはこの保険証が必要になりますので、大切に保管しましょう。
介護保険サービスを受ける手続きは?
介護保険は、医療保険のように保険料を払っていれば誰でも利用できるというわけではなく、事前に市区町村の介護保険窓口に申請して「要介護認定」を受けなければなりません。
要介護認定の申請
本人または家族が、市区町村の役場にある介護保険の窓口(介護保険課・高齢者支援課など)に、要介護認定の申請をします。地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・成年後見人・介護保険施設の職員が代わりに申請することもできます。
この時、介護保険被保険者証が必要になります(第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証)。
また、手続きの中で主治医意見書が必要になるので、かかりつけの医師に書いてもらいましょう。かかりつけの医師がいない場合、市区町村が指定する医師の診察を受けます。
訪問調査
市区町村の職員や市区町村から委託を受けた調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態について聞き取り調査します。また、家族の方には普段の様子について確認します。
判定
一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書をコンピューターに入力し、要介護度を判定します。
二次判定
一次判定の結果と訪問調査の特記事項をもとに、医療や福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で審議が行われ、要介護度が決定します。
認定
申請した方に、以下のいずれかの認定結果が通知されます。
- 要支援1・2
- 要介護1~5
- 非該当(自立)
認定結果は、原則として申請した日から30日以内に通知することになっています。
非該当とされた場合や、希望より要介護度が低く評価された場合、不服を申し立てることができます。不服を申し立てるときは、結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に、都道府県の設置する「介護保険審査会」に申立てをしてください。