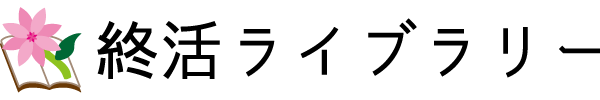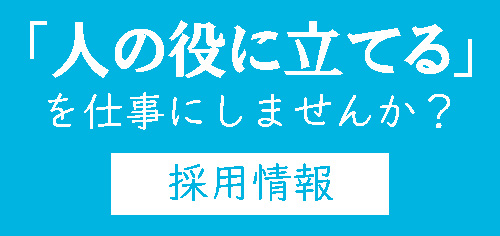宗教・宗派による香典袋の種類と選び方
通夜や葬儀・告別式に持っていく香典は、相手の宗教・宗派に合わせた香典袋に包んで持参します。宗教・宗派によって、主に表書きや水引、包みのデザインなどに違いがあります。
できれば、訃報を受け取った時に、どの宗教なのか聞いておきたいところです。
1) 宗教・宗派が分らない場合の香典袋
宗教・宗派が分らない場合は、各宗教共通で使うことができる、表書きが「御霊前」となっている香典袋を選びます。
ただし、浄土真宗では人が亡くなったらすぐに仏になるとの教えがあり、通夜・告別式でも「御仏前」とするのが正しいと言われています。
2)仏式
宗教が分らなくても仏教ということが分っている場合は、どの宗派でも使うことができる「御香典」「御香料」とします。日本の仏教で檀家数が多いのは浄土真宗であり、「御霊前」はふさわしくないからです。
仏式であっても「御仏前」は、お通夜や告別式には使いません。四十九日などの葬儀よりあとの法要で使います。
3)神式
「御玉串料」が一般的です。「御霊前」でも構いません。
4)キリスト教
「お花料」が一般的です。カトリックでは、「ミサ料」も使います。
水引について
弔事に関しては、二度と起こらないようにという意味も含めて、水引は結び目が解けない「結び切り」が使われます。
結び切りの一種で「あわび結び(あわじ結び)」も使われていますが、この水引はお祝い事にも用いられている一般的に使われているものです。
「両輪を互いに引っ張る事により更に固く結びあう」ということから、「末永くお付き合いする」という意味合いもあり、お布施などにも用いられます。
また、白と黄色の水引も弔事で使われます。
しかし、葬儀や弔問の時に包むお香典には、やはり相応しくありません。
四十九日など法事での利用が一般的です。